かつては「コスパ最強」「自由なカスタマイズ」といえば自作PC。しかし最近では「自作PCは時代遅れ」「もうやめとけ」という声も聞かれるようになりました。
この記事では、自作PCがなぜネガティブに見られがちなのか、その理由を詳しく掘り下げたうえで、「こんな人には自作PCがまだまだおすすめ!」という視点もご紹介します。
1. なぜ「自作PCはやめとけ」「時代遅れ」と言われるのか?
1-1. コスパが悪くなってきた
かつては「同じスペックなら自作の方が圧倒的に安い」と言われていましたが、現在では状況が大きく変わっています。
- GPU(グラボ)の価格が高騰:特にNVIDIAのRTXシリーズは需要過多やマイニング需要の影響で価格が跳ね上がり、自作のコストを押し上げています。
- OSが別途必要:自作PCではWindowsライセンスを自分で用意しなければならず、1万〜2万円の追加費用になります(BTOならプリインストールが一般的)。
- BTOのセールが強すぎる:特にドスパラ、フロンティア、マウスコンピューターなどのBTOは定期的に爆安セールを実施しており、自作よりも安く手に入る場合が増えています。
このように、価格の面での「自作の優位性」は薄れ、むしろBTOの方が安いという逆転現象すら見られます。
1-2. 組み立ての難易度が高い
自作PCには「自由さ」と引き換えに「責任」が伴います。初めて組む人にとっては、意外とハードルが高いです。
- 電源が入らない:ケーブルの接続ミスや電源ユニットの選定ミスで「通電しない」トラブルが起きがちです。
- 相性問題:CPUとマザーボードのBIOSが対応していなかったり、メモリが正常に認識されないなど、知識がないと対応が難しい問題も。
- 配線の難しさ:ケーブルマネジメント、フロントパネルの接続など、説明書だけでは理解しにくいポイントが多い。
- OSのインストールやBIOS設定:初心者には不慣れなUEFI/BIOSの設定画面も、最初はとっつきづらいです。
BTOならこれらはすべて工場出荷時に済んでおり、電源を入れればすぐに使える点が初心者に好まれる理由です。
1-3. スペック重視の時代じゃない
現代の多くのPC用途では、ハイスペックマシンを必要としないことが増えています。
- ネット・SNS・動画視聴:YouTube、X(Twitter)、Zoomなどの利用なら、内蔵GPU付きのCPUでも快適に動作します。
- オフィス作業:WordやExcel、ブラウザの操作においては、Core i5やRyzen 5のノートでも問題ありません。
- 軽量なゲーム:原神、VALORANT、マイクラ程度であれば、ミドルスペックでも十分対応可能。
このため「ハイスペックな自作PCを組む=用途に対してオーバースペック」と言われるケースも増えています。
1-4. メーカー製やBTOの品質が向上
一昔前のBTOは「格安だけど品質が悪い」というイメージがありましたが、今は違います。
- 電源やマザーボードの品質向上:80PLUS認証の電源ユニットや、有名メーカー製マザボが標準搭載されることも多くなりました。
- 冷却設計の進化:以前は「排熱が弱い」「うるさい」などの問題もありましたが、現在は高効率な空冷/水冷が標準化され、静音性や冷却性も高いです。
- デザイン性の改善:ゲーミングモデルを中心に、RGBライティングやガラスパネル搭載モデルなど、見た目にもこだわったPCが増えています。
- サポート・保証の安心感:1〜3年保証付き、故障時には無償対応など、初心者にとって非常に大きな安心材料になります。
つまり「安いけど性能も品質も妥協しない」BTOパソコンが登場している現在、あえて自作を選ぶ必要性が減ってきたのです。
2. それでも「自作PCがおすすめ」な人の特徴とは?
2-1. パーツにこだわりたい人
自作PC最大の魅力は「構成をすべて自分で決められる」点です。以下のようなこだわりを持つ人には、自作が圧倒的に向いています。
- 見た目:ガラスサイドパネル、ARGBファン、ライティングコントロールで“映えるPC”を作りたい人。
- 冷却性能:水冷、ハイエアフローケース、大型ヒートシンクで温度を徹底管理したい人。
- 静音性:静音ファン、防振ケース、ファンコントロールの調整など、耳に優しい環境を求める人。
- ブランド選び:ASUS、MSI、GIGABYTEなど、パーツメーカーにこだわりたい人。
BTOでは基本構成が決まっており、こうしたこだわりをすべて実現するのは難しいため、自作PCは理想を追求したい人に最適です。
2-2. PCの知識を深めたい人
自作PCは「学び」にも大きな価値があります。作業を通して自然と身につく知識は、将来にも役立ちます。
- PC構成の理解:CPU、GPU、チップセット、メモリ、電源など、ハードウェア全体を体系的に学べる。
- トラブルシューティング能力:不具合が起きたときの原因特定力や解決力が身につく。
- 将来のキャリアにも有利:IT系・エンジニア職、サポート職などで知識が武器になる。
「動けばいい」ではなく「中身も理解したい」という探究心がある人には、自作は非常に有意義な経験になります。
2-3. 長期的にアップグレードしたい人
自作PCは構成がオープンで自由。将来的な拡張性・柔軟性の面でも圧倒的に優れています。
- GPUだけ交換:グラフィック性能が必要になったら、グラボだけを新調できる。
- メモリ増設:空きスロットを活用すれば、8GB→16GB→32GBと徐々に強化可能。
- ストレージ追加:M.2スロット、SATAポートなどを活かし、SSD/HDDを自在に増設。
- OSや冷却も刷新可能:将来Windows 12やより高性能な冷却方式にも柔軟に対応可能。
メーカー製PCやノートPCではできない「自由な拡張」を求めるなら、自作はベストな選択です。
2-4. 趣味として楽しめる人
自作PCは、ただの道具ではなく「一つのクリエイティブな趣味」としても楽しめます。
- パーツ選びのワクワク感:価格・性能・ビジュアルを比較しながら選ぶ楽しさ。
- 組み立ての達成感:完成して電源が入った瞬間の喜びは、自作ならでは。
- 自分だけの唯一無二のPC:世界に一つだけの構成・デザインを形にできる。
- SNSやブログで発信できる:ビルドログやレビューを投稿して同じ趣味の仲間と繋がれる。
「作ること自体が楽しい」と思える人にとって、自作PCはコスパや効率を超えた価値をもたらします。
3. 自作PCが“本当に時代遅れ”になる未来とは?
現時点ではまだ多くの人にとって「自作PC」は有力な選択肢です。しかし、テクノロジーの進化によって、将来的には自作という行為そのものが“時代遅れ”とされる可能性もあります。以下では、そうなるかもしれない未来のシナリオを紹介します。
クラウドゲーミングの進化
「GeForce NOW」「Xbox Cloud Gaming」「Amazon Luna」など、クラウドゲーミングは確実に進化を続けています。
- 高性能なゲーミングPCが不要:ネット回線さえあれば、スマホ・タブレット・安価なノートPCでもAAAタイトルが快適に遊べるように。
- デバイスの買い替え頻度が激減:ローカル性能ではなく、クラウド側のサーバースペックに依存するため、個人での自作ニーズが減少。
- 定額制で常に最新環境:常に最新GPUでのプレイが可能になるサブスクリプション型の時代が来るかもしれません。
このような未来が当たり前になれば、「高性能なゲーミングPCを自分で作る理由」がかなり薄れてしまうでしょう。
AIによる自動最適構成の時代
AIの進化によって、ユーザーの用途や予算に合わせて「自動的に最適なPC構成を提案してくれる」時代が近づいています。
- 人間の知識を超える選定力:膨大なパーツ情報と相性データをAIが分析して、最適なパーツ選定・組み合わせを提示。
- ワンクリックで注文:構成から発注、組み立て、配送までを自動化した「完全無知でも安心」なサービスが登場する可能性。
- 自作の意義が薄れる:人間が悩んで選ぶというプロセス自体が「非効率」とされる時代になれば、自作=無駄とみなされることも。
「構成を考えるのが楽しい」という人以外にとって、自作PCが不要になる日は案外近いのかもしれません。
ARMベースのPCが主流化
AppleのM1/M2シリーズの成功を皮切りに、今後ARMアーキテクチャがPC市場で主流となっていく可能性があります。
- x86からARMへ移行:WindowsやLinuxもARM対応が進み、パフォーマンス・省電力性の点でARMが勝るシーンが増加。
- 自作向けARMパーツの不足:ARMベースのCPUやマザーボードは現在のところ、ほとんどが完成品として供給されており、個人がカスタマイズ・自作するのが困難。
- 「モジュールで組む文化」の終焉:スマホと同じように、SoC(System on Chip)化が進めば、パーツ単位で交換する概念そのものが消滅。
もしこの流れが加速すれば、「CPUとマザーボードを選んで組む」という従来の自作文化そのものが衰退していく可能性があります。
まとめ:それでも“今はまだ遅くない”
上記のような未来は、まだ完全に現実化しているわけではありません。しかし、技術革新のスピードを考えると、「自作PCは当たり前」という時代はあと5年、10年で終わるかもしれません。
だからこそ「今この瞬間に、自作PCを組んで楽しむ」という体験は、とても貴重なものになるでしょう。
まとめ|「やめとけ」に流されず、自分に合った選択を
「時代遅れ」「やめとけ」と言われる自作PCですが、それが当てはまるかは人それぞれです。
以下に当てはまる人には、自作PCは今でも魅力的な選択肢です。
- 自分だけのこだわり構成を組みたい
- PCの知識を深めたい
- 長期的にアップグレードしながら使いたい
- PC作りを趣味として楽しみたい
逆に、
- とにかく安く済ませたい
- すぐに使いたい
- 詳しくない・トラブルが不安
という人にはBTOやメーカー製PCが適しているかもしれません。
最後に|あなたのスタイルに合ったPC選びを
自作PCは「作る楽しさ」「知識の向上」「カスタマイズ性」など、単なるコスパ以上の魅力を持っています。
他人の声に流されず、自分のスタイルに合った選択をすることが、満足のいくPCライフへの第一歩です。


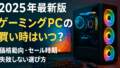
コメント