ゲーム開発者やゲーマーの間で話題となることの多い「Steamの手数料」。とくにインディーゲーム開発者にとっては、利益に直結する重要な問題です。「Steam 手数料 高い」というキーワードが検索される背景には、実際の手数料体系やその負担感に対する疑問や不満があります。この記事では、Steamの手数料が本当に高いのか、その金額や仕組み、さらに他のプラットフォームとの比較を通じてその理由を詳しく解説していきます。
Steamの基本的な手数料構造
Steamでは、ゲームを販売した際に発生する売上に対して、基本的に30%の手数料がかかります。つまり、1,000円のゲームを販売した場合、開発者の手元には約700円が入り、残りの300円はValve(Steamの運営会社)に支払われる仕組みです。
スライド制による手数料の変化
2018年から、Steamは売上規模に応じて手数料を減らす「スライド制」を導入しました。
- 累計売上が1,000万ドルを超えた場合、手数料は25%に減少
- 累計売上が1億ドルを超えると、手数料はさらに20%に
とはいえ、この恩恵を受けられるのはAAAクラスの大作タイトルに限られており、大多数のインディーゲームは引き続き30%の手数料が適用されます。
その他の手数料・コスト
Steamには販売手数料以外にも、開発者が負担する費用があります。
Steam Direct 登録料
Steamでゲームを公開するには、Steam Directという仕組みを利用し、1タイトルごとに100ドル(約15,000円前後)の登録料を支払う必要があります。この費用は、売上が1,000ドルを超えると返金される仕組みです。
コミュニティマーケット手数料
Steamでは、ゲーム内アイテムの売買ができる「コミュニティマーケット」があります。ここでも、販売価格の5%(Valveに2%、ゲーム開発者に3%)の手数料が取られます。小さな金額とはいえ、アイテムの売買が活発なゲームでは無視できない収益源とされます。
手数料が「高い」と言われる理由を詳しく解説
1. 他のプラットフォームとの手数料比較
近年、Steam以外にも魅力的な条件を提示するゲーム販売プラットフォームが増えてきました。とくにEpic Games Storeやitch.ioは、開発者にとってより利益が残りやすい仕組みを提供しています。以下の表は各プラットフォームの収益配分を比較したものです。
| プラットフォーム | 開発者の取り分 | 備考 |
|---|---|---|
| Steam | 70% | 1,000万ドル以上の売上で25%、1億ドル超で20%に低下 |
| Epic Games Store | 88% | Unreal Engine使用時のロイヤリティ割引あり |
| itch.io | 90〜100% | 手数料は開発者自身が自由に設定可能 |
このように見ると、Steamの30%という手数料は、特別に安いとは言えません。特に売上がまだ多くない開発者にとっては、Epicやitch.ioのほうが明らかに「収益率が高い」選択肢となります。
2. 中小開発者への負担が大きい
Steamでは「誰でもゲームをリリースできる」という強みがある一方で、その手数料構造は一律適用されるため、売上の少ない開発者にとっては大きな負担になります。
例えば、ある開発者がゲームを1,000本販売し、1本あたり1,200円の売上があったとします。総売上は120万円になりますが、Steamが30%を取ることで実際の手取りは約84万円です。さらにここから登録料(100ドル=約1.5万円)、為替手数料、源泉徴収、所得税などが引かれ、最終的に手元に残るのは70万円以下ということもあり得ます。
これでは、開発期間にかけた数ヶ月の生活費や外注費すら賄えないケースもあります。つまり、「利益が出るようになる前にコストがのしかかる」のが、Steamが“中小開発者に厳しい”と言われるゆえんなのです。
3. 独占的な市場シェアによる価格支配力
Steamは長年の実績により、PCゲーム市場において“絶対的な存在”としての地位を築いています。2025年現在も、PCゲームの売上の約7割がSteam経由で発生しているとされ、多くのユーザーにとって「PCゲーム=Steam」という認識が根付いています。
この支配的な立場があるからこそ、開発者側も「高いと感じても、Steamに出さないと売れない」というジレンマに陥りやすいのです。仮に他プラットフォームの方が利益率が良くても、そもそもそこでは十分な顧客がいなければ、意味をなしません。
結果として、多くの開発者がSteamの30%という手数料を「高すぎる」と感じながらも、それを受け入れざるを得ない構造になっているのです。
4. 手数料以外の隠れコストも存在
Steamでの販売には、実は目に見えない形でのコストも発生しています。
- 登録料:1タイトルあたり100ドル(約1.5万円)
- 税務処理:アメリカへの源泉徴収(最大30%)が発生する場合あり
- 返金ポリシー:2時間以内・14日以内であれば無条件返金→収益が取り消される
特にインディー開発者にとって、これらの“細かな出費”がボディブローのように効いてきます。「思ったより利益が出ない」という原因の多くは、こうした隠れコストにもあります。
まとめ:高い手数料は市場力と引き換え
Steamの手数料が「高い」と言われる理由は、単に数字の話だけではなく、その影響力の強さゆえに他の選択肢が事実上少ないこと、そして小規模な開発者ほど負担が大きい構造にあることです。
ただし、これを“搾取”と見るか、“市場へのアクセス料”と見るかは、それぞれの立場や戦略によって異なるでしょう。重要なのは、開発者が自身の状況に合った最適な販売プラットフォームを選べるよう、こうした実態を理解しておくことです。
それでもSteamを使う理由を詳しく解説
Steamの手数料が高いと感じられる一方で、それでも多くの開発者がSteamを主な販売チャネルとして選び続けています。その理由は、単なる販売プラットフォームの枠を超えた、強力な“総合支援インフラ”としての価値にあります。
1. 世界中に数億人規模のアクティブユーザーが存在
Steamは月間アクティブユーザーが1億人以上、同時接続ユーザー数も3,000万人を超えるなど、PCゲーム市場では圧倒的なユーザーベースを誇ります。ゲームを公開するだけで、これだけの潜在的プレイヤーにリーチできることは、他のどのプラットフォームにも真似できない大きな強みです。
特にリリース直後の“新作”カテゴリや、ジャンル別ランキングなど、ユーザーに見つけられるチャンスが豊富に用意されています。
2. 決済、セール、アップデート管理などが一括で提供される
Steamにゲームを登録すれば、以下のような機能が自動的に提供されます:
- クレジットカード・PayPal・各国の通貨への対応
- 自動セール反映(ウィンターセール、サマーセールなど)
- ゲームのバージョン管理・アップデート配信
- 地域別価格設定
つまり、開発者自身が複雑な支払いシステムやセールの仕組みを構築する必要は一切なく、Steamがすべてのバックエンド処理を引き受けてくれるため、本来の「ゲーム開発」に専念できます。
3. レビュー機能による可視性の向上
Steamでは、ゲーム購入者が簡単にレビューや評価を残すことができ、それがストアページにリアルタイムで反映されます。これにより、品質の高いゲームであればポジティブな口コミが広がり、自然と売上にもつながる仕組みが整っています。
また、レビューの数が増えることで「信頼できる作品」として認知され、Steamのおすすめアルゴリズムにも優遇されやすくなります。
4. ウィッシュリストと通知機能の存在
Steamのウィッシュリスト機能は、ゲームに興味を持ったユーザーが後で購入できるよう“お気に入り登録”しておくためのものです。セールが始まったタイミングで自動的に通知が飛ぶため、開発者側はリマインダー広告などを使わなくても売上を後押しできます。
とくにセール時期には、ウィッシュリストに入れていたユーザーからの購入率が跳ね上がるため、この機能は非常に重要です。
5. まとめ:30%の手数料に見合う“時間と安心の対価”
Steamの30%という手数料は確かに高額に感じられるかもしれませんが、得られる恩恵を考えると「集客、運営、決済、マーケティング支援」が一体となった、非常に効率的な販売環境です。
これらをすべて自前で構築・管理することを考えれば、30%の支払いはむしろ合理的とも言えます。特にリソースが限られているインディー開発者にとっては、「開発に集中できる」環境を提供してくれるSteamは、今なお魅力的な選択肢であると言えるでしょう。
今後の動向と開発者の選択肢
2025年現在でも、Steamの手数料体系に大きな変更はありません。ただし、Epic Games Storeが積極的なマーケティングや開発者優遇策を展開していることから、競争の中で将来的に手数料の見直しが行われる可能性もあります。
開発者にとって重要なのは、Steam一本に依存するのではなく、自社販売や他プラットフォームとの併用など、多角的な収益モデルを模索することです。
まとめ
Steamの手数料は確かに高いと感じる部分もありますが、それだけの利便性と露出機会が用意されているのも事実です。中小の開発者にとっては、その手数料が収益に大きく影響するため、販売戦略の選択が重要になります。
他のプラットフォームと併用しながら、リスクを分散しつつ収益性を最大化していく姿勢が、これからの開発者には求められるでしょう。
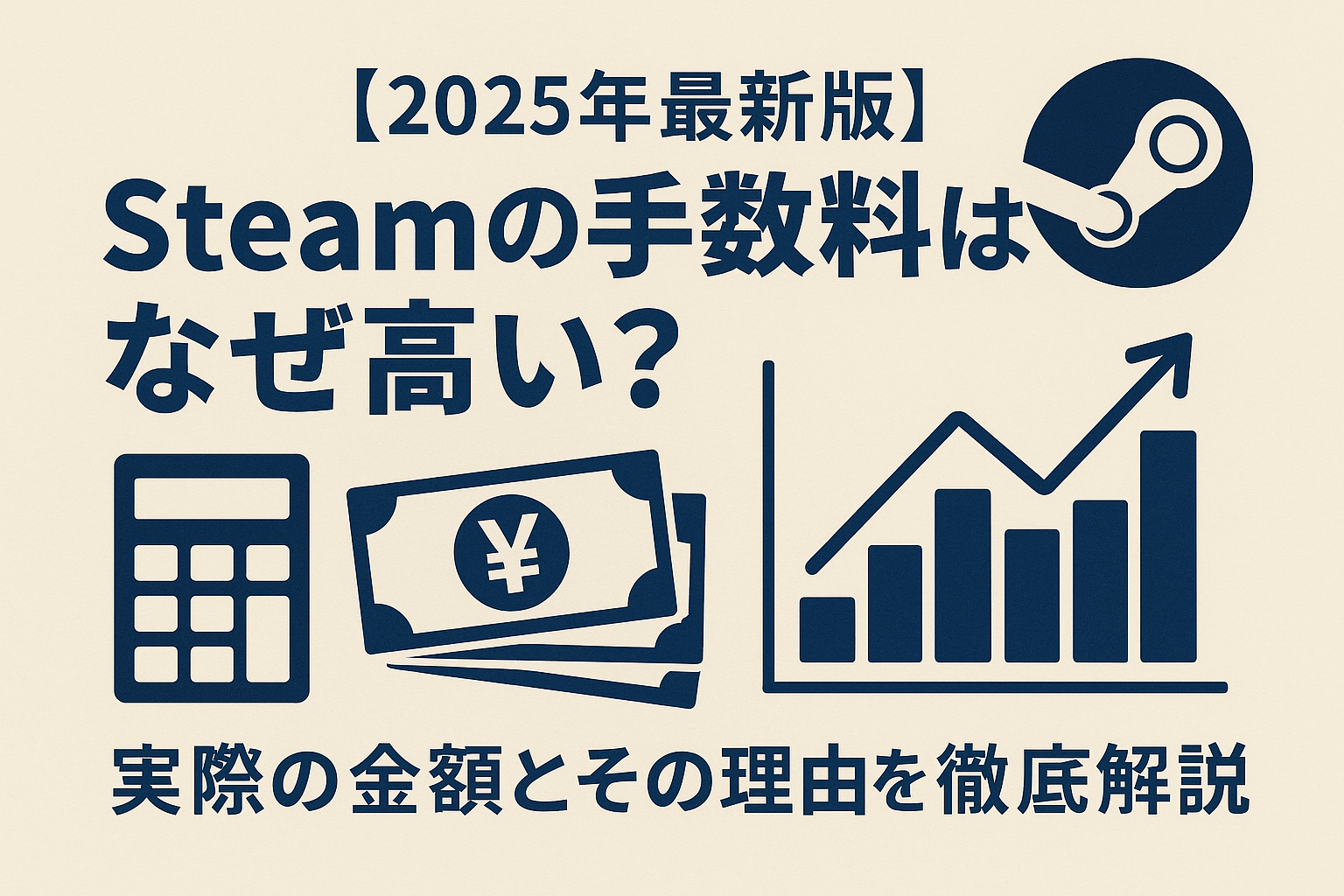
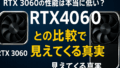

コメント